-
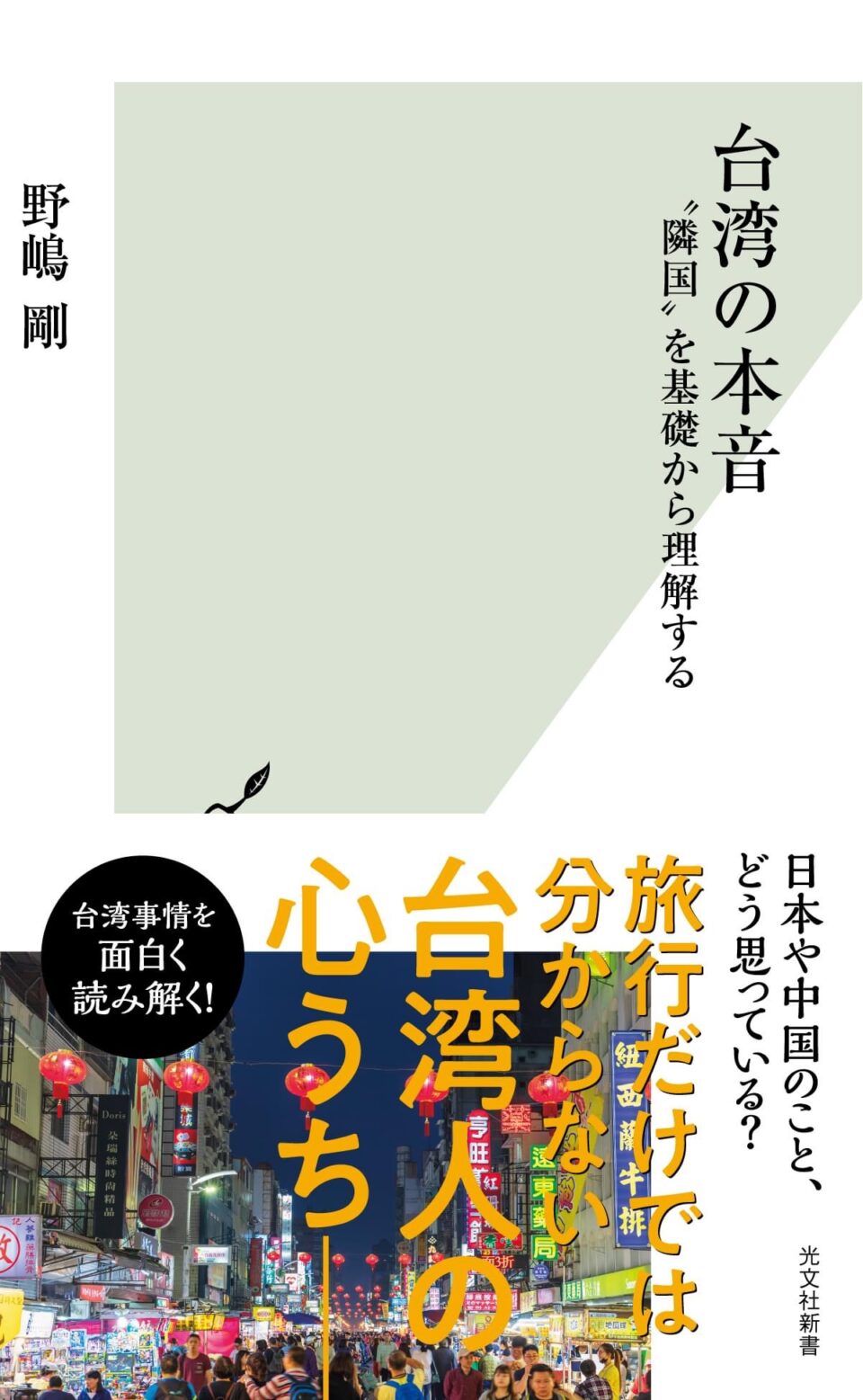
台湾の本音 ”隣国”を基礎から理解する
コロナ前は200万人超の日本人が訪れ、観光地として人気が高い台湾。「台湾有事」という言葉が紙面を賑わすこともあり、日本の関心は高くなっている。しかし、私たちは台湾をどれほど知っているだろうか。中国と台湾の関係は? 首都はどこにある? 国連に非加盟なのはなぜ? 隣の島でありながら、私たちはその歴史や事情をあまり知らない。本書では、6つの問いからそんな台湾という〝国〟の姿を詳らかにしていく。
-

新中国論: 台湾・香港と習近平体制
香港と台湾に対してかつてないほどの強硬な姿勢を見せる中国。いま、中国に何が起きているのか。中国という国家の本質を、台湾と香港を介してみた新しいかたちの中国論!
《目次》
はじめに
第1章「台湾化」と「香港化」の狭間で
第2章 なぜ台湾と香港は中国にとって「特別」なのか
第3章 中国指導者にとっての台湾・香港問題
第4章 台湾・香港にとっての「中国」と本土思想
第5章 失われた「文化中国」の連帯
第6章 グローバル化する台湾・香港問題
第7章 日本は台湾・香港にどう向き合うべきか
第8章 台湾・香港は「坑道のカナリア」
付録:2021年の「歴史決議」で記された台湾・香港問題
関連年表
参考文献 -

蒋介石を救った帝国軍人 ――台湾軍事顧問団・白団の真相
宿敵はなぜ手を結んだか。膨大な蒋介石日記、生存者の証言と台湾軍上層部の肉声を集めた。敗戦国軍人の思い、蒋介石の真意とは。解説 保阪正康
-

香港とは何か
香港は終わらない
香港が歴史的転換点を迎えている。一国二制度のもと特別行政区として五〇年間の高度な自治が保証されるはずだった。ところが中国・習近平政権は力による「中港融合」を押し進め、一国二制度を形骸化させる国家安全法を香港の頭越しに決めた。世界を驚かせた二〇一九年の大規模抗議デモに続き、香港問題はいま米中新冷戦の最前線に浮上している。東洋の真珠と呼ばれ、日本とも関係の深い国際金融都市・香港を知りたいすべての人に届ける一冊。激動の香港、いま起きていること、そして未来
【目次より】
第一章 境界の都市
第二章 香港アイデンティティと本土思想
第三章 三人の若者――雨傘運動のあと
第四章 二〇一九年に何が起きたか
第五章 映画と香港史
第六章 日本人と香港
第七章 台湾の香港人たち
第八章 中国にとっての香港
第九章 香港と香港人の未来 -
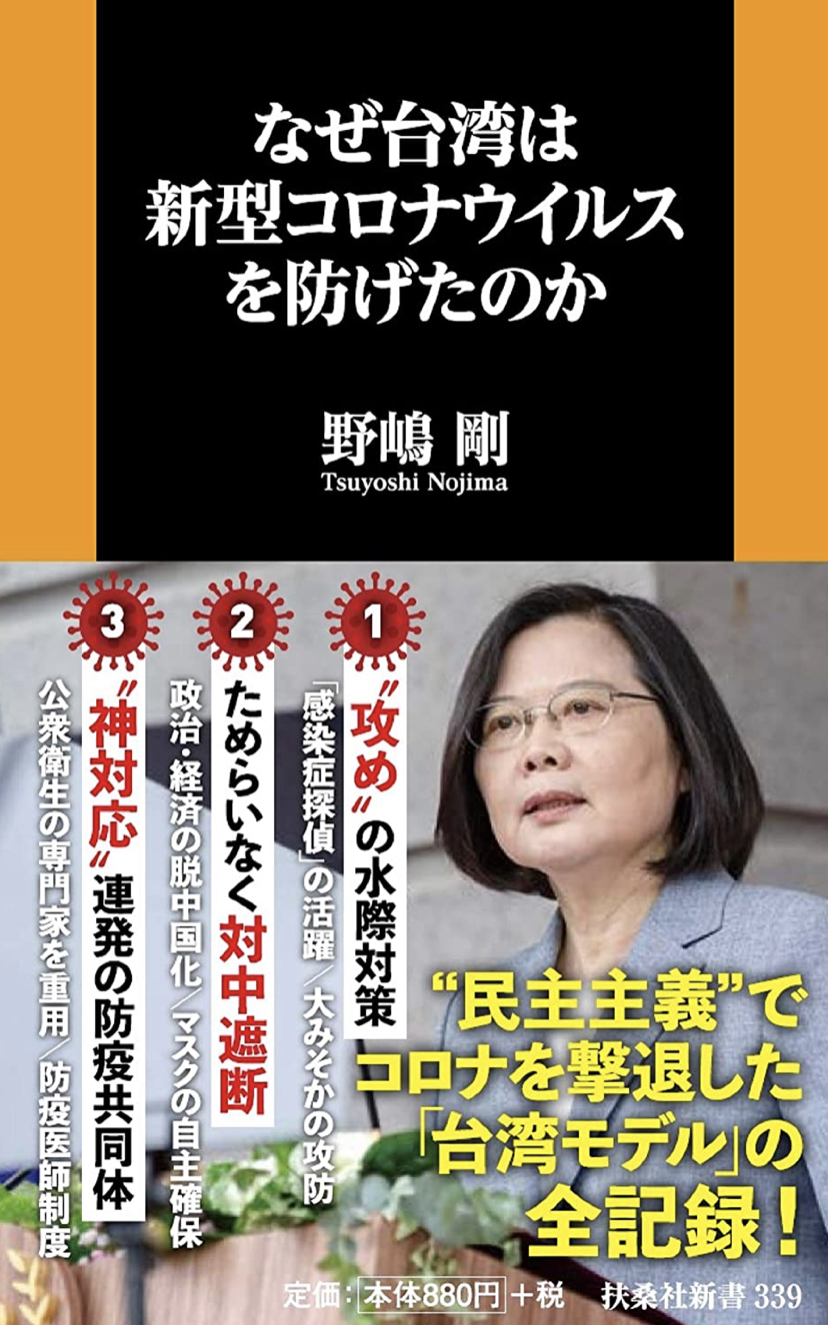
なぜ台湾は新型コロナウイルスを防げたのか
わずか感染者442人、死者7人
(日本:感染者約17,000人、死者約900人)※2020/5/31現在
世界最速で「検疫」と「隔離」を徹底できた本当の理由
1“攻め"の水際対策――「感染症探偵」の活躍/大みそかの攻防
2ためらいなく対中遮断――政治・経済の脱中国化/マスクの自主確保
3“神対応"連発の防疫共同体――公衆衛生の専門家を重用/防疫医師制度
“民主主義"でコロナを撃退した「台湾モデル」の全記録!【目次】
プロローグ 大晦日の24時間
第一章 世界最速の「水際対策」
第二章 マスク政治学
第三章 台湾の新型コロナウイルス対策を総ざらいする
第四章 「SARSの悪夢」から台湾が学んだもの
第五章 蔡英文政権の強力布陣と「脱中国化」路線
第六章 「疫病の島」から「防疫の島」へ
第七章 中国もWHOも信じなかった台湾
第八章 中国に支配されるWHO
第九章 政治への熱意が作った「防疫共同体」
第十章 台湾に学ぶ「アフターコロナ」 -

タイワニーズ 故郷喪失者の物語
彼らがいたから、強く、深くつながり続けた
戦前は「日本」であった台湾。戦後に「中国」になった台湾。1990年代の民主化後に自立を目指す台湾。戦争、統治、冷戦。常に時代の風雨にさらされ続けた日本と台湾との関係だが、深いところでつながっていることができた。それはなぜか。 台湾と日本との間を渡り歩いて「結節点」の役割を果たす、多様な台湾出身者の存在があったからである――まえがきより
台湾をルーツに持ち、日本で暮らす在日台湾人=タイワニーズたち。元朝日新聞台北支局長の筆者が、彼らの肖像を描き、来歴を辿りながら、戦後日本の裏面史をも照らす。
【目次】
・蓮舫はどこからやってきたか
・日本、台湾、中国を手玉にとる「密使」の一族 辜寛敏&リチャード・クー
・「江湖」の作家・東山彰良と王家三代漂流記
・おかっぱの喧嘩上等娘、排除と同化に抗する 温又柔
・究極の優等生への宿題 ジュディ・オング
・客家の血をひく喜びを持って生きる 余貴美子
・「551蓬莱」創業者が日本にみた桃源郷 羅邦強
・カップヌードルの謎を追って 安藤百福
・3度の祖国喪失 陳舜臣
・国民党のお尋ね者が「金儲けの神様」になるまで 邱永漢 -

台湾とは何か (ちくま新書)=最新刊
新たな時代を迎えつつある台湾。台湾アイデンティティの隆盛やヒマワリ運動、「中華民国の台湾化」によって、台湾政治、中台関係、日中関係のいずれも過去の枠組みでは簡単に分析できない難しい局面を迎えています。総統選で勝利した民進党の蔡英文が迎えるチャレンジとは何か。中台関係を改善させた国民党がなぜ惨敗を喫したのか。日本も台湾に対する新しい視座が求められていることを提言しています。
平成28年度 第11回樫山純三賞(一般書部門)受賞。
-

故宮物語 政治の縮図、文化の象徴を語る90話
故宮という『フィルター』を通し、日本、台湾、中国が絡みあう東アジアの近現代史と国際政治を描く
なぜ習近平は「中華民族の偉大なる復興」を掲げるのか―。
中国と台湾に存在する二つの故宮は、日中戦争と国共内戦の産物であり、アジア近現代史の縮図である。戦後台湾の蒋介石にとっては「中国正統政権」の象徴とされ、今日も中台交流の最前線にある。中国では「中華」があらゆる場で強調され、政権交代を控えた台湾でも故宮の分院「南院」は「中華かアジアか」で揺れている。
アジア随一の美の殿堂・故宮を、歴史・政治・文化のあらゆる面から精緻に解読する一冊。 -
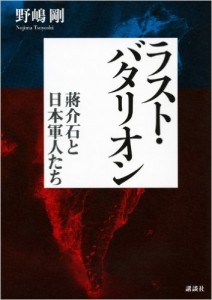
ラスト・バタリオン 蒋介石と日本軍人たち
戦後の約20年間、台湾において旧大日本帝国軍人による大規模かつ組織的な軍事支援がおこなわれていました。密航して台湾に渡り、蒋介石の軍事顧問となった彼らは「白団」と呼ばれました。その名はリーダーを務めた元陸軍少将・富田直亮が「白鴻亮」という中国名を名乗っていたことに由来します。しかし、よく考えてみれば旧敵たる蒋介石を、どうして日本人たちがさまざまな危険を冒して海を渡って助けなければならなかったのでしょうか? 逆に、どうして日本の旧軍人たちに助けを乞いたいと蒋介石は考え、実行に移したのでしょうか? 蒋介石のいわゆる「以徳報怨」演説と敗戦国日本への寛大な政策への恩義、反共というイデオロギーでの一致、日本人の勤勉さへの蒋介石の畏敬の念……。さまざまな要素が絡まりあって史上例を見ない不思議な軍事顧問団が形成されていったのです。ただ、そこには当然、それぞれの思惑、建前と本音が存在しました。本書は足かけ七年を費やしてアメリカ、台湾、日本に散在する未公開資料を渉猟し、関係者を取材した記録です。蒋介石という政治家の実像と白団の等身大の姿が、いまはじめて浮かび上がってきます。
戦争終結当時、国民党政権は「以徳報怨」政策の下で、中国大陸にいた百万を超える日本の軍人たちの日本帰還を進める一方、彼らを参謀として、また技術者として留用しようとした。これは共産党も同様だった。蒋介石は、支那派遣軍総司令官だった岡村寧次を戦犯として処罰せずに側に置いただけでなく、台湾に撤退する前後には、日本に帰国した岡村の斡旋(あっせん)で日本の軍人たちを集め、参謀として、また軍人教育に当たる人員として雇用した。その集団はリーダーの富田直亮の中国語名・白鴻亮から、「白団」と呼ばれる。本書は研究書ではないが、その「白団」をめぐる歴史研究のひとつの到達点を示していると言って良い。
従来、白団については資料的制約により解明が進まなかったが、著者は新たな資料を用い、この課題の多くを克服した。重要なのは、蒋介石日記や国史館の文書を用いただけでなく、これまで主に回想録などしかなかった日本側の動向について、戸梶金次郎日記を用い、また数名の生存者や遺族にインタビューをおこない、白団の人々の内面から白団史を描くことに本書は成功している。そして、白団の後方支援組織だった富士倶楽部の集めた蔵書や資料を国防大学図書館で確認したことも、大変重要な貢献である。さらに、帰国してからの白団の軍人たちの足跡や、資料公開に対する動向を扱ったことで、これまで「資料的制約」があったことの背景を浮き彫りにしている。
ーー日本経済新聞朝刊2014年6月15日付/川島真書評から抜粋 -

認識・TAIWAN・電影 映画で知る台湾
映画から見えてくる台湾社会の現実
急速に活気を取り戻す台湾映画。本書は朝日新聞元台北支局長が映画という窓を通して台湾を覗き込んだ「台湾論」である。「日台」や「外省人」「格差」など、今の台湾社会を映し出す映画を紹介しながら、台湾社会のトレンドや現実を、監督や俳優のインタビューを交えながら描き出す。目次
Part1 映画に描かれた素顔の台湾
Scene1 映画で「台湾と日本」を問い続ける
[CINEMA]「海角七号」「セデック・バレ」「KANO」
[Interview1]魏徳聖 監督
Scene2 台湾ドキュメンタリーの力
[CINEMA]「天空からの招待状」「抜一条河」「刪海経」
[Interview2]斉柏林 監督
Scene3 外省人2世の思い
[CINEMA]「軍中楽園」「白銀帝国」
[Interview3]鈕承沢 監督
Scene4 格差社会の矛盾を突く
[CINEMA]「郊遊〈ピクニック〉」「あなたなしでは生きていけない」「白米炸彈客」
[Interview4]蔡明亮 監督 李康生 氏
Scene5 「環島」による「認識台湾」
[CINEMA」「練習曲」「遠い道のり」「不老騎士」
[Interview5」陳懐恩 監督
Scene6 台湾文化を知る
[CINEMA]「祝宴!シェフ」「モンガに散る」「父の初七日」
[Interview6]陳玉勲 監督
Scene7 「あの時代」を照らし出す
[CINEMA]「あの頃、君を追いかけた」「GF*BF」「九月に降る風」
[Interview7]九把刀 監督
Scene8 台湾の優しさ、台湾人の優しさ
[CINEMA]「聴説」「光にふれる」「白天的星星」
[Interview8]李烈 プロデューサー兼女優
Scene9 台湾映画に欠かせないアイテム
[ITEM]「バイク」「喫茶店」「同性愛」「軍人教官」
[Interview9]侯孝賢 監督
Scene10 台湾映画の歴史と課題
[Interview10]龍応台 前文化部長 -
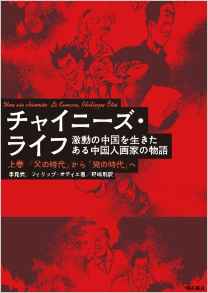
チャイニーズ・ライフ――激動の中国を生きたある中国人画家の物語【上巻】「父の時代」から「党の時代」へ
人生とは与えられた現実の中でひたすら生きることだ──
1950 年代半ば、中国南西部・雲南省の省都昆明に生まれた少年、小李(シャオ・リー)。小李の行く手には、中国ひいては世界を揺るがせた大躍進政策、文化大革命、四人組批判、そして鄧小平の改革開放政策による驚異的な経済発展が待ち受けていた。激動の中国を生きたごく普通の少年の成長を通して、リアルで等身大の「チャイニーズ・ライフ」が浮かび上がる。現代中国に起きた変化は我々の想像を絶する世界だ。中国人一人ひとりが、その巨大な叙事詩の体験者であり、目撃者なのである。その人生の変化はあまりにも激しく、理不尽であり、その変化に巻き込まれて生きる人々は、過去を飲み込み、前に進んでいくしかない。なぜなら人生とは与えられた現実の中でひたすら生きることだからだ。そんな「チャイニーズ・ライフ」が、本書を手に取った方々の眼前に浮かび上がってくることを期待したい。──訳者解説より
-

チャイニーズ・ライフ――激動の中国を生きたある中国人画家の物語【下巻】「党の時代」から「金の時代」へ
人生とは与えられた現実の中でひたすら生きることだ──
1950 年代半ば、中国南西部・雲南省の省都昆明に生まれた少年、小李(シャオ・リー)。小李の行く手には、中国ひいては世界を揺るがせた大躍進政策、文化大革命、四人組批判、そして鄧小平の改革開放政策による驚異的な経済発展が待ち受けていた。激動の中国を生きたごく普通の少年の成長を通して、リアルで等身大の「チャイニーズ・ライフ」が浮かび上がる。現代中国に起きた変化は我々の想像を絶する世界だ。中国人一人ひとりが、その巨大な叙事詩の体験者であり、目撃者なのである。その人生の変化はあまりにも激しく、理不尽であり、その変化に巻き込まれて生きる人々は、過去を飲み込み、前に進んでいくしかない。なぜなら人生とは与えられた現実の中でひたすら生きることだからだ。そんな「チャイニーズ・ライフ」が、本書を手に取った方々の眼前に浮かび上がってくることを期待したい。──訳者解説より
-
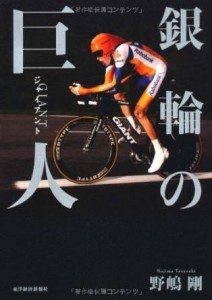
銀輪の巨人
とてつもない自転車メーカー「台湾巨大機械」とは何者なのか!?
エコでクリーンで健康的な移動手段として、世界的な自転車ブームが起きている。その中心にいるのが、世界最大の自転車ブランド、GIANT(ジャイアント、正式名称は「巨大機械工業」)だ。
同社は、自転車レースの最高峰「ツール・ド・フランス」を制し、フレームの世界シェアでトップに立っている。同社は台湾で生まれ、いまも台湾に本社を置く台湾メーカーだ。自転車産業といえば、かつて日本勢が抜群の実力を誇っていた。ブリジストン、丸石、ミヤタ、ナショナル……。だが、いまや昔日の面影はない。シマノのような部品メーカーを除けば、日本の自転車産業は壊滅してしまったといっていい状況だ。なぜなのだろうか?
そこに現在のエレクトロクス産業をはじめとする日本製造業の不振の構図が二重写しになっている。つまり、自転車産業は日本製造業の将来を暗示しているのだ。台湾で生まれた世界最大メーカーの知られざる実態に迫りつつ、日本の産業界で強烈な警鐘を鳴らす衝撃のノンフィクション一冊。筆者は朝日新聞元台湾支局長。著者は朝日新聞国際部デスク。社会部、厦門大学客員研究員、イラク・アフガンでの戦場取材、台湾支局長などを歴任したいわば非ビジネス分野のエキスパートだ。そのような現役記者が著した本書は事実とインタビューにこだわった、読み物風に仕上がっているビジネス書だ。経営学特有の流行り言葉の乱発や無理なこじつけもなく清々しい。
かつて世界一の自転車輸出国であった日本が凋落し、中国と台湾が台頭しはじめたのは20年前からだ。しかし、中国はともかく、台湾は安モノを作ることで日本を追い込んだわけではない。日本製自転車の平均輸出単価は1990年には4万円を超えていた。ところが2000年になると2万円を割り込み、2010年には1万円まで落ち込んでいる。いっぽう、台湾の平均輸出単価は2002年には124ドルだったが、2011年には380ドルに上昇しているのだ。日本は量販店対応の安モノしか作れなくなっているのだ。家電業界でも同じような事態が進行中なのかもしれない。家電メーカーは自社の「経験」から学ぶより、自転車産業という「歴史」から学ぶべきなのだろう。
----2012年6月6日 成毛真「新刊超速レビュー」より抜粋---- -
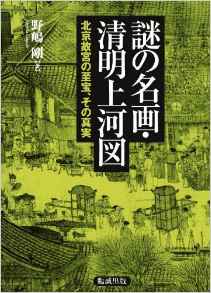
謎の名画・清明上河図 北京故宮の至宝、その真実
中国美術の至宝にまつわるミステリー 北宋、開封の都を描いたとされる中国屈指の名画「清明上河図」。 来歴、作者、描かれている情景と時代、後世に与えた影響…。その作品のすべては深遠な謎と波乱に満ちたストーリーに満ちている。 鑑賞の方法から作品成立の裏側まで、知られざる名画を味わい、愉しむ。
「本書の最大の特色は、その記述の多くが、著者自身の実体験に基づいていることにある。『開封人はスープ好き』などという情報は、そういった取材抜きにはありえない」
「日本に伝わっている模写も、実際に取材した上で紹介してくれている」
「中国の遼寧省まで出かけてゆかりの人物を訪ねて話を聞くことを忘れない」
「開封市にある『清明上河園』というテーマパークに足を運んだ、(中略)このあたり、いかにもジャーナリストらしいアプローチが生かされた、たのしい読みものになっている」
----2011年2月3日「週刊読書人」/円満字二郎氏書評から抜粋 -

ふたつの故宮博物院 (新潮選書)
戦争と政治に引き裂かれ、「北京」と「台北」に分かれた、ふたつの故宮。同じ名をもつ東洋の二大博物館が、相容れない仲となって約半世紀が経つ。しかしいま、中国と台湾の歩み寄りが、両故宮をにわかに接近させつつある。数々の歴史的秘話や、初の「日本展」へ向けどのような水面下の動きがあったかを明らかにしながら、激動を始めた両故宮に迫る最新レポート。
同じ中華文明の文物だけを収蔵、展示するための博物館が、しかも全く同じ名前で、なぜ大陸と台湾とに二つも存在するのか、甚だ不思議なことである。ジャーナリストである著者も初めて故宮を訪れた学生時代からその不思議さに引っかかっていたという。二〇〇七年に台北特派員になったのを機に、故宮の歴史に関わる名だたる関係者を取材し続け、大陸台湾の間を飛び回って、得た貴重な材料をもとに本書を書き上げた。
辛亥革命後、一九二五年から始まった博物館としての故宮は、四九年に中国が大陸と台湾とに分裂したことで、二つになった。以来、中台関係に影響されつつ、それぞれの体制下でも、常に政治運動の的にされてきた。その足跡はこのおよそ九十年の中国史を生き写ししているようにも思われる。
著者は、政治・外交という独自の視点からこの歴史を辿(たど)り、そこに隠された権力者の思惑及び文物が持つ、「中国ならではの」政治的な意義をえぐり出そうとしている。
ーーー2011年6月21日 朝日新聞社朝刊/楊逸氏書評から抜粋 -
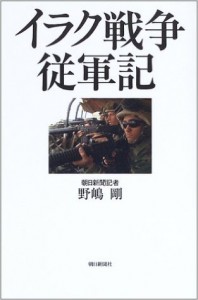
米軍と一ケ月行動を共にした記者がつぶさに目撃した「生」のイラク戦争。命を賭けた従軍取材の興奮と恐怖、「戦争報道」の現実を伝える。

